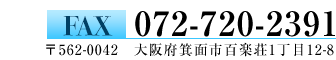硬化収縮率は下記の計算式により求めます。
硬化収縮率(%)=(硬化物比重-硬化前比重)÷硬化物比重×100
ビス系ビニルエステル樹脂の硬化前比重(液体比重)は、1.04
硬化物比重は、1.14です。
計算式に当てはめると
硬化収縮率(%)=(1.14-1.04)÷1.14×100≒8.8
硬化収縮率は、8.8%となります。8.8%はメーカーの公表値(8.0%程度)より、多少大きい値ですが妥当な範囲内だと思います。実際に塗布作業を行って、膜厚計やルーペで確認された方は「もっと収縮している」と感じると思います。なぜ、そう感じるかを確認していきます。
ひとつは、計量用のサンプルの形状にあるようです。規格では硬化物比重を求めるサンプルは、角柱状の硬化物を使用しますが、実際の現場施工では1回の塗布作業で0.2kg~0.4kg/㎡、ガラスマットを使用した積層作業でも1.0kg~1.2kg/㎡で塗布厚では1.0mm以下であるので、1mm厚の薄板状硬化物サンプルで硬化収縮率を求めてみます。


同様に薄板状のサンプルを計量し、硬化物比重は1.15でした。
硬化収縮率の計算式に当てはめると、収縮率は、9.6%でした。
大きな変化は、ないようです。この樹脂を一回の塗布作業で1mm厚に塗ることはないので、本来は0.2~0.4mm厚の薄板状サンプルを作成したいのですが、私たちでは正確に作成できないため、作成、試験方法を変更しなくてはならないので、時間があればチャレンジします。
今回は他に何点か試してみました。ビニルエステル樹脂に対し、各同量(重量比)のガラスマット、骨材Aを添加した2種とエポキシ樹脂の硬化収縮率を求めてみました。試験は各種3体のサンプルを作成し、結果は3体の平均値です。
| 種類 | 硬化収縮率(%) 角柱状 | 硬化収縮率(%) 薄板状状 |
| ビニルエステル樹脂 単体 | 8.8 | 9.6 |
| ビニルエステル樹脂 + ガラスマット | 10.1 | 19.4 |
| ビニルエステル樹脂 + 骨材A | 9.65 | 11.5 |
| エポキシ樹脂 | 1.68 | 1.9 |
すべて、薄板状の数値が高くなりました。ビニルエステル樹脂はスチレンを40%程度含んでいるので、硬化時に空気と触れる面積が大きい薄板状ではスチレンの飛散量が大きくなるのでしょうか。特にガラスマットは、表面に凹凸があるので表面積が多くなるため、値もかなり高めでした。エポキシ樹脂は縮まないようですね。
ガラスマットの収縮率19.3%は、私たちの施工時の感覚に少し近付いた値でした。ガラスマット1Ply+サーフェスマット+トップコートでは、40%程度の膜厚減少があるように思っています。サーフェスマットやトップコートの1回の塗布厚は、ガラスマットよりも塗布量が少なく薄くなるのでスチレンの飛散割合が増加し硬化収縮が大きくなる可能性があると思いますが、定かではないので次回に確認したいと思います。
骨材添加については、骨材A以外の無機骨材も試しました。おもしろいのが、種類によって、ビニルエステル樹脂単体の硬化収縮率を上回る骨材、下回る骨材がありました。これは、おそらくビニルエステル樹脂は硬化時の発熱温度の差が硬化収縮率に影響するため、骨材の熱伝導率が関係しているのではないかと思いますが、わたしには解りません。先輩方から収縮を抑えるためには、無機骨材等を使えば良いと教えられましたが、種類や添加の割合によっては、誤った扱いをしていたのかもしれないです。
防食被覆層の塗膜厚の計画にあたっては、多少の余裕が必要で、初めて扱う樹脂では、試験施工による膜厚の確認は必須事項ですね。
期待していた結論までは至らず、課題が増えてしまいました。
少しずつ、解決したいですね。
「自分の、目で見て、手で触れてみて」これが、一番良いですね。